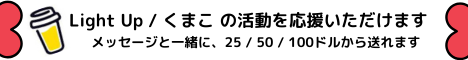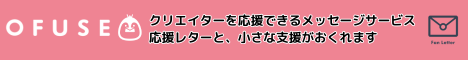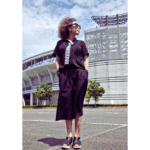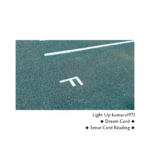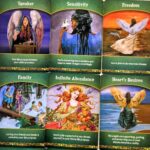以前書いた「時間の幅」の記事から
少し前に「時間の幅、誰が決めたの?」という記事を書いて、その中で古代バビロニアの60進法について触れました。
でも、その記事を書いた後に動画を見ていたら、「60進法を作ったのはシュメール人だった」という話が出てきて。え、シュメール人?
そもそもシュメール人って何者なんだろう?という疑問が湧いてきたので、少し調べてみました。
シュメール人という謎の民族
調べてみると、シュメール人って本当に謎だらけの民族だった。
チグリス・ユーフラテス川流域に世界最古の都市国家を築き、それがメソポタミア文明の先駆けとなったとされているけれど、シュメールの民族と言語がどこから来てどこへ消えたのかは、いまだ解明されていないらしい。
来歴の謎ゆえに「シュメール人は宇宙人」とまで囁かれるほど。まあ、それは流石に…と思うけれど、確かに彼らの文明の高さは驚くべきものがある。
**世界最古の文字(楔形文字)、都市国家、車輪、そして暦。**これらすべてを発明したとされているんです。
60進法の起源について、諸説いろいろ
以前の記事では古代バビロニアの60進法について書いたけれど、実際はもっと複雑だった。
紀元前3000年から紀元前2000年の頃から、シュメールおよびその後を継いだバビロニアでは、六十進法が用いられたとあるように、シュメール人が先に60進法を使い始めて、それがバビロニアに受け継がれたという流れのよう。
でも面白いのは、シュメール人は、紀元前3500年頃までは十進法を用いており、十進法から進化する形で六十進法に移行したということ。
最初は私たちと同じ10進法だったのに、なぜ60進法に変えたんだろう?
なぜ60だったのか?
これについては本当にいろんな説があって、正解は分からないみたい。
月の朔望周期説:60は、両手の指の数である10と一年における月の朔望周期の回数である12との最小公倍数として意味のある数
約数が多い説:60がその特性として、1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30、60という多くの約数をもっていたから分割に便利
天体観測説:1年は約360日、月は約30日で満ち欠けを繰り返します。これらの数字は、いずれも60の倍数あるいは約数であり、60進法が天文学的な計算や暦の作成に極めて適していた
どの説も説得力があるけれど、きっとすべてが複合的に絡み合っていたのかもしれない。
実は6・10進法だった?
さらに興味深かったのは、シュメールの数体系は純粋な60進法ではなく、6・10進法だったという説もあること。
縦の楔(V)が1を、横の楔(<)が10を表していて、59に達するまでは十進法的に表記されているということで、10進法をベースにしながら60で区切るという、なんだかハイブリッドなシステムだったみたい。
4000年以上経った今でも
そして驚くのは、シュメール人が築き上げた60進法の世界は、約4000年以上の時を超え、驚くべきことに現代社会にも深く根付いていますということ。
私たちが当たり前に使っている「1時間60分」「1分60秒」「円は360度」。これらすべてが、メソポタミアの平原で星空を見上げていたシュメール人たちの知恵から来ているなんて。
謎だらけだからこそ面白い
結局、シュメール人がなぜ60進法を選んだのか、はっきりとした答えは分からない。
でも、その謎だらけな感じが逆に魅力的だと思う。4000年以上前の人たちが考えた「時間の区切り方」を、今でも私たちが使い続けているって、なんだかロマンを感じませんか?
月の満ち欠けを見ながら、星の動きを追いながら、彼らが見つけた「60」という数字の魔法。
それが今でも、私たちの毎日の時間を刻んでいる。そう思うと、時計を見るのも少し違って感じられるような気がします。
✧━━━━━━━━━━━━━✧
自分にコードをつなげよう
My rhythm, my light
✧━━━━━━━━━━━━━✧